スポンサーサイト
熊本の朝鮮飴のこと
2014年05月14日
5月1日に阿蘇にいってきました。
お目当ては、JR阿蘇駅にできた「レストラン火星」と阿蘇神社と朝鮮飴。
このブログでは、朝鮮飴のことを書いています。
阿蘇神社をあとにして、熊本までもどってきました。
熊本は、加藤清正公が作った熊本城があります。清正公は土木や建築に才能があった方だったようです。あの石垣をみると、素晴らしいの一言ですもんね。熊本城の石垣は、美しく、ちょっと色気があるので好きです。加藤家が改易となった後は、細川氏の城下町となりました。でも、加藤清正公の人気は衰えず、細川氏もその点にはかなり配慮して治世を行ったといわれています。
加藤清正公というと、虎退治・・・を思い出しますが、今回熊本に立ち寄ったのも、実は清正公に関係あるモノが欲しかったからなのでした。
熊本でのお目当ては、もちろんお菓子です。
それは・・・・・老舗 園田屋の「朝鮮飴」です。
お店を訪ねたら、お~~~~…すごい。古くてステキ♪

(写真の吹き出しみたいなものは、お店の紹介がかかれているものです)

お店の名前の上に創業天正年間・・とあります。
天正年間って安土桃山時代だ~・・・。
お店のなかで、朝鮮飴と柿球肥の試食をいただきながら、ちょっとだけお店の方とお話をしました。いただいた、朝鮮飴と柿球肥、どちらも懐かしい味でした。朝鮮飴の味は小さいときから知っている味。実は父の好物でしたから、小さいときから食べてました。ボンタン飴の味に似てるとも思いました。ボンタン飴も父の好物。なるほど好きなはずだわ・・と改めて思いました。柿球肥は、柿がきらいなので、大丈夫かな・・って思いましたが、全く心配無用といったおいしさ。こちらの方が甘いお菓子でした。
さて、なんで朝鮮飴という名前なのでしょうか?
答えは、いただいたしおりに書いてありました。もともと、このお菓子は園田屋の開祖 初代園田武衛門によって創製されたもので、当初は、長生飴といっていたようです。加藤清正が特に寵用したお菓子で、文禄、慶長の役に、朝鮮に携行し、長期の口糧としてよく保存に耐えたことに感銘せられ、朝鮮飴といわれるようになったそうです。
主な原料はもち米と水あめと砂糖。

日持ちはしますが、長くおくと固くなります。が、その時はお湯をかけたり温めると柔らかくなるそうでさすが、備蓄に向いているお菓子であります。
なんで、名前が餅でなくて飴なんだろう?
家に戻って食べながらふと思いました。またお店に行って聞いてこようかな。
これが朝鮮飴 小箱の方は、粉から出して1枚1枚銀紙で包んだものだそうです。
今の時代に合わせた仕様ということでしょうか。確かに粉が散らないので便利です。
普通の朝鮮飴はこんな風に片栗粉のなかにはいってます。
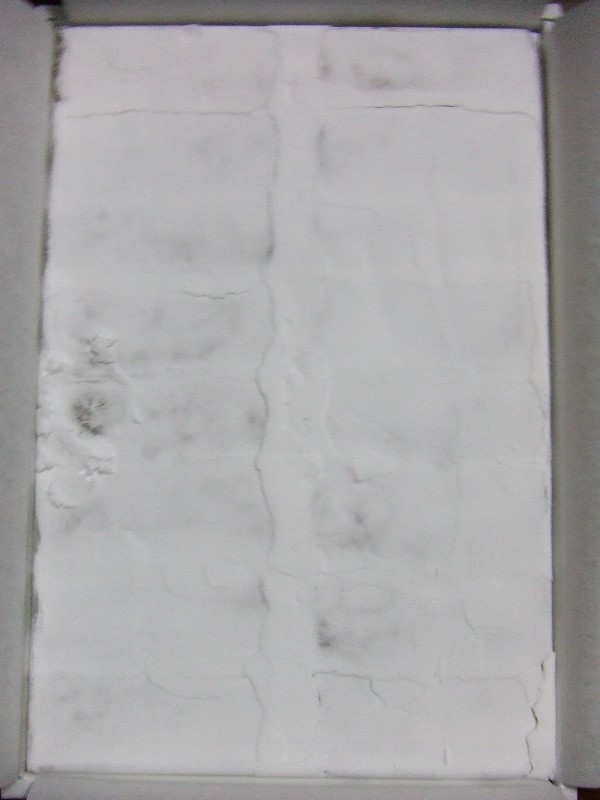
ちょっと掘ってみましょう(笑)

柿球肥は、この朝鮮飴に肥後特産の柿の風味を加えたお菓子です。こちらは新しいお菓子だそうですが、出来上がったのは明治36年だそうです。園田屋は400年以上の歴史があるので、明治時
代はまだ時代としては若い方になるのかも。
柿球肥です。

こちらは少し黒っぽい。周りの白いところは砂糖です。
なので、食べるとダイレクトに砂糖の甘さが口に広がります。
苦いお茶、コーヒーがあいますね~。

シンプルな形と味はお茶菓子にぴったり。朝鮮飴に比べて、モダンな感じ。
小さいときからよく知っているつもりだったお菓子でしたが、歴史を知るとちょっと味わいが増す気がします。いつでもそうですが、お菓子には物語があって、それが楽しい&美味しいのだ・・と改めて思いました。
園田屋はお菓子だけでなく建物がとても良くて、魅力的。また行きたいな~。店の外に求人募集の張り紙がしてあって、熊本に住んでたら応募するな~ってちょっとだけ思いました。
熊本にはほかにも調べたいお菓子があるので、また行かなくっちゃね。次回のお愉しみ・・、なんだか近頃は宿題が多いなあ~。
*****************************
~長崎街道(シュガーロード)について~
長崎街道(シュガーロード)は江戸時代に整備された脇街道の一つで、小倉の常盤橋を起点として長崎にいたるまでの路線です。長崎の出島に入った砂糖はこのルートを通って大阪や江戸に運ばれました。この砂糖が通った道沿いには、さまざまなお菓子が生まれることとなります。そして、時代が下って、炭鉱が華々しい頃にそのお菓子たちは筑豊で大きく花開く事になります。今では全国的に有名になっている【ひよこ】や【チロルチョコ】などは筑豊生まれのお菓子です。
私はこのシュガーロードを歩いて、お菓子が生まれた土壌、文化などを調べたいと常々思っていた・・というわけです。小倉~長崎までの宿場町に繁栄したお菓子、今でも残っている古いお菓子、新しい時代のお菓子、絶滅しかかっているお菓子など調べますよ。そして長崎まで調べたら、南蛮菓子の故郷、ポルトガルへ・・・と野望をいだいております。
******************************
このブログのサイドバーにあるテーマ 長崎街道(シュガーロード)で今まで書いたことを見ることができます.
当ブログ内の文章、写真、その他の無断転用、転載を固く禁じます
お目当ては、JR阿蘇駅にできた「レストラン火星」と阿蘇神社と朝鮮飴。
このブログでは、朝鮮飴のことを書いています。
阿蘇神社をあとにして、熊本までもどってきました。
熊本は、加藤清正公が作った熊本城があります。清正公は土木や建築に才能があった方だったようです。あの石垣をみると、素晴らしいの一言ですもんね。熊本城の石垣は、美しく、ちょっと色気があるので好きです。加藤家が改易となった後は、細川氏の城下町となりました。でも、加藤清正公の人気は衰えず、細川氏もその点にはかなり配慮して治世を行ったといわれています。
加藤清正公というと、虎退治・・・を思い出しますが、今回熊本に立ち寄ったのも、実は清正公に関係あるモノが欲しかったからなのでした。
熊本でのお目当ては、もちろんお菓子です。
それは・・・・・老舗 園田屋の「朝鮮飴」です。
お店を訪ねたら、お~~~~…すごい。古くてステキ♪

(写真の吹き出しみたいなものは、お店の紹介がかかれているものです)

お店の名前の上に創業天正年間・・とあります。
天正年間って安土桃山時代だ~・・・。
お店のなかで、朝鮮飴と柿球肥の試食をいただきながら、ちょっとだけお店の方とお話をしました。いただいた、朝鮮飴と柿球肥、どちらも懐かしい味でした。朝鮮飴の味は小さいときから知っている味。実は父の好物でしたから、小さいときから食べてました。ボンタン飴の味に似てるとも思いました。ボンタン飴も父の好物。なるほど好きなはずだわ・・と改めて思いました。柿球肥は、柿がきらいなので、大丈夫かな・・って思いましたが、全く心配無用といったおいしさ。こちらの方が甘いお菓子でした。
さて、なんで朝鮮飴という名前なのでしょうか?
答えは、いただいたしおりに書いてありました。もともと、このお菓子は園田屋の開祖 初代園田武衛門によって創製されたもので、当初は、長生飴といっていたようです。加藤清正が特に寵用したお菓子で、文禄、慶長の役に、朝鮮に携行し、長期の口糧としてよく保存に耐えたことに感銘せられ、朝鮮飴といわれるようになったそうです。
主な原料はもち米と水あめと砂糖。

日持ちはしますが、長くおくと固くなります。が、その時はお湯をかけたり温めると柔らかくなるそうでさすが、備蓄に向いているお菓子であります。
なんで、名前が餅でなくて飴なんだろう?
家に戻って食べながらふと思いました。またお店に行って聞いてこようかな。
これが朝鮮飴 小箱の方は、粉から出して1枚1枚銀紙で包んだものだそうです。
今の時代に合わせた仕様ということでしょうか。確かに粉が散らないので便利です。
普通の朝鮮飴はこんな風に片栗粉のなかにはいってます。
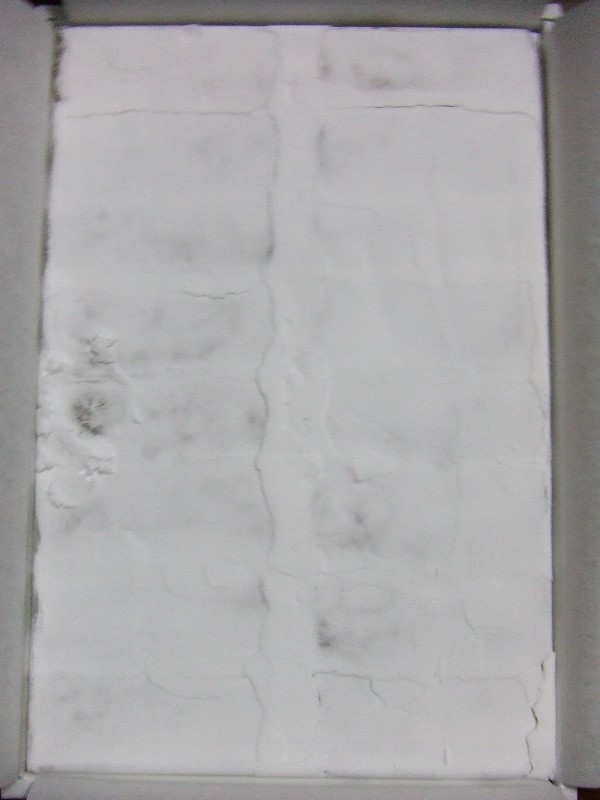
ちょっと掘ってみましょう(笑)

柿球肥は、この朝鮮飴に肥後特産の柿の風味を加えたお菓子です。こちらは新しいお菓子だそうですが、出来上がったのは明治36年だそうです。園田屋は400年以上の歴史があるので、明治時
代はまだ時代としては若い方になるのかも。
柿球肥です。

こちらは少し黒っぽい。周りの白いところは砂糖です。
なので、食べるとダイレクトに砂糖の甘さが口に広がります。
苦いお茶、コーヒーがあいますね~。

シンプルな形と味はお茶菓子にぴったり。朝鮮飴に比べて、モダンな感じ。
小さいときからよく知っているつもりだったお菓子でしたが、歴史を知るとちょっと味わいが増す気がします。いつでもそうですが、お菓子には物語があって、それが楽しい&美味しいのだ・・と改めて思いました。
園田屋はお菓子だけでなく建物がとても良くて、魅力的。また行きたいな~。店の外に求人募集の張り紙がしてあって、熊本に住んでたら応募するな~ってちょっとだけ思いました。
熊本にはほかにも調べたいお菓子があるので、また行かなくっちゃね。次回のお愉しみ・・、なんだか近頃は宿題が多いなあ~。
*****************************
~長崎街道(シュガーロード)について~
長崎街道(シュガーロード)は江戸時代に整備された脇街道の一つで、小倉の常盤橋を起点として長崎にいたるまでの路線です。長崎の出島に入った砂糖はこのルートを通って大阪や江戸に運ばれました。この砂糖が通った道沿いには、さまざまなお菓子が生まれることとなります。そして、時代が下って、炭鉱が華々しい頃にそのお菓子たちは筑豊で大きく花開く事になります。今では全国的に有名になっている【ひよこ】や【チロルチョコ】などは筑豊生まれのお菓子です。
私はこのシュガーロードを歩いて、お菓子が生まれた土壌、文化などを調べたいと常々思っていた・・というわけです。小倉~長崎までの宿場町に繁栄したお菓子、今でも残っている古いお菓子、新しい時代のお菓子、絶滅しかかっているお菓子など調べますよ。そして長崎まで調べたら、南蛮菓子の故郷、ポルトガルへ・・・と野望をいだいております。
******************************
このブログのサイドバーにあるテーマ 長崎街道(シュガーロード)で今まで書いたことを見ることができます.
当ブログ内の文章、写真、その他の無断転用、転載を固く禁じます


