スポンサーサイト
上島珈琲店で丸ぼうろ
2014年09月01日

東京に戻っていたKさんから聞いた話。
ある日、お兄さんが珈琲と丸ぼうろを持って帰ってきたそうで。
丸ぼうろは、北部九州ではコンビニでも見かけるくらい、ちっとも珍しいお菓子ではありませんが、東京で見ることはほとんどないお菓子なので、これどうしたの・・・と根堀、葉掘りお兄さんに聞いて、それは上島珈琲店で売っているものだ・・・ということが分かったとのこと。
上島珈琲ね~・・ 。UCCコーヒーといった方がわかりやすいかしらね。
UCCが丸ぼうろを販売してるとはね。
なんで、丸ぼうろ?
もしかして創業者が九州人?なんて、いろいろと話が飛躍しましたが、調べてみたら、創業者は関西の人?みたいで、創業の地は神戸でした。違うね。こればかりはUCCに問い合わせてみないとわからないね。・・という話でおしゃべりは終了。
で、本日、博多駅まで行ったので、上島珈琲店によって確認してみましたら、本当に売ってる。
これ、ちゃんと佐賀のお菓子屋さん(大坪製菓)が作っている。佐賀ぼうろね。
ちょっとモダンなパッケージに入っていると丸ぼうろもちょっとかっこいい感じ。
西洋菓子なんて書いてある。
丸ぼうろは、もともとはポルトガルから伝わったボーロがもとになっているといわれている南蛮菓子。
だから?かもしれませんが、コーヒーにあいます。
このことで、丸ぼうろが全国区になってくれればいいな~・・と、佐賀をルーツに持つ私としては思ってます。
ちなみに、ぼうろ・・といえば、京都の衛生ぼうろ(卵ぼうろ)とかそばぼうろを想像する方も多いと思います。どちらも、クッキーのようなお菓子。このお菓子たちを想像しながら、佐賀の丸ぼうろを食べると、あれ?湿気が来てる・・と思うかもしれません。丸ぼうろは堅いクッキーのようなお菓子ではありません。柔らかいお菓子です。くれぐれもびっくりしないように。(笑)
それから、丸ぼうろは佐賀が有名ですが、大分県の中津市のも有名なんですよ~。
興味のある方は調べてみてね(笑)
*****************************
~長崎街道(シュガーロード)について~
長崎街道(シュガーロード)は江戸時代に整備された脇街道の一つで、小倉の常盤橋を起点として長崎にいたるまでの路線です。長崎の出島に入った砂糖はこのルートを通って大阪や江戸に運ばれました。この砂糖が通った道沿いには、さまざまなお菓子が生まれることとなります。そして、時代が下って、炭鉱が華々しい頃にそのお菓子たちは筑豊で大きく花開く事になります。今では全国的に有名になっている【ひよこ】や【チロルチョコ】などは筑豊生まれのお菓子です。
私はこのシュガーロードを歩いて、お菓子が生まれた土壌、文化などを調べたいと常々思っていた・・というわけです。小倉~長崎までの宿場町に繁栄したお菓子、今でも残っている古いお菓子、新しい時代のお菓子、絶滅しかかっているお菓子など調べますよ。そして長崎まで調べたら、南蛮菓子の故郷、ポルトガルへ・・・と野望をいだいております。
******************************
このブログのサイドバーにあるテーマ 長崎街道(シュガーロード)で今まで書いたことを見ることができます.
当ブログ内の文章、写真、その他の無断転用、転載を固く禁じます
夏休みの自由研究??
2014年08月16日
いつも、長崎街道(シュガーロード)などスイーツ関連の私のブログを読んでくださってありがとうございます。
夏休みの自由研究の影響でしょうか?近頃のブログの解析をみると、検索ワードは圧倒的に長崎街道、シュガーロード、松屋、長崎 お菓子の名前・・などが多いようです。
近頃は、何を調べるにも、まずネット検索・・なので、こんな検索結果となっているのでしょう。
検索ワードを見ていると、へ~こんなことまで検索するのね・・というものに遭遇します。
例えば、あるお饅頭の直径とか、その断面の写真とか・・・。
実際に買うのが惜しいのか?
それとも遠方で買いに行けない?取り寄せられない?
郷土菓子を調べているものとしては、できれば、実際にお店に行って、買って、食べてほしいな~と思ってます。郷土菓子はその地域に根差したお菓子が多いので、それを育てた地域、風土、もっといえば、その空の下で食べるのが一番おいしい・・と思っているからです。現地で作っているお菓子屋さんから話がきければ、尚、ラッキ~。(忙しい時は聞いちゃだめですよ)おいしさ倍増です。
何を調べるにも、自分の足を使う。
フィールドワークは大切だし、一番楽しい部分でもあります。
どうぞ、この一番楽しい部分を大切に。

写真は鳥栖の水田屋さんのすずめ最中
こんな楽しい形のお菓子に出会えるのも、お菓子の調べものの醍醐味です。
夏休みの自由研究の影響でしょうか?近頃のブログの解析をみると、検索ワードは圧倒的に長崎街道、シュガーロード、松屋、長崎 お菓子の名前・・などが多いようです。
近頃は、何を調べるにも、まずネット検索・・なので、こんな検索結果となっているのでしょう。
検索ワードを見ていると、へ~こんなことまで検索するのね・・というものに遭遇します。
例えば、あるお饅頭の直径とか、その断面の写真とか・・・。
実際に買うのが惜しいのか?
それとも遠方で買いに行けない?取り寄せられない?
郷土菓子を調べているものとしては、できれば、実際にお店に行って、買って、食べてほしいな~と思ってます。郷土菓子はその地域に根差したお菓子が多いので、それを育てた地域、風土、もっといえば、その空の下で食べるのが一番おいしい・・と思っているからです。現地で作っているお菓子屋さんから話がきければ、尚、ラッキ~。(忙しい時は聞いちゃだめですよ)おいしさ倍増です。
何を調べるにも、自分の足を使う。
フィールドワークは大切だし、一番楽しい部分でもあります。
どうぞ、この一番楽しい部分を大切に。
写真は鳥栖の水田屋さんのすずめ最中
こんな楽しい形のお菓子に出会えるのも、お菓子の調べものの醍醐味です。
「風立ぬ」で復活 シベリアというお菓子
2014年07月03日
ある日のことでした。
お菓子のことを検索していた時のこと。あるHPで、カステラとあんこの相性は思っているよりもよく、例えば、シベリアというお菓子が・・・・・云々。と書かれた文章を見つけました。
シベリア????
お菓子??
聞いたことがないぞ?
お菓子なら調べなくては・・
というわけで、今回のテーマは【シベリア】です。
写真は、横浜のコティーベーカリーから取り寄せたものです。

見ての通りの姿。
カステラとカステラの間に羊羹状のあんこ。
羊羹だからちゃんと固まっている。
あんこをはさんでいるのではなくて、トレーにカステラを敷いてそのうえに羊羹を流し込んで作るらしい。側面に漏れているところがあって、その製法を伺わせます。手間がかかっているお菓子です。
(お菓子・・といっていいかなあ。菓子パンの仲間になるのかも。明治から大正にかけて作っていたのはパン屋さんらしい。)
調べていると、
どうも明治時代の後半から大正時代にかけて生まれたお菓子で、ミルクホール(今でいう喫茶店のこと)での定番お菓子だったらしい。
いつ、どこで、だれが作り始めたのかは不明。
なぜこのお菓子の名前が【シベリア】なのか?
羊羹の部分がをツンドラを走るシベリア鉄道にみたてた・・・とか、シベリアの凍土をあらわしたとか・・・いろいろな説があるようです。コティーベーカリーのHPにいろんな説が紹介されてますので興味のある方は読んでみてください。
販売エリアは、首都圏を中心にした東日本と中部地方。近畿地方を中心とした西日本や九州ではなじみがないお菓子らしい。確かに、見たことはないが、Facebookでコメントをいただいた中に、九州で買ったというものがあって、全くないわけではないようです。
首都圏・・というと、これは東京出身の友人に聞いてみるのが早い・・・で、聞いてみましたところ、羊羹カステラといっていたということ。牛乳と一緒に食べるとおいしかったとのこと。私より若い友人が知っているということは、ごく最近まであちこちで販売されていたということでしょう。
味は、私が食べたコティーベーカリーのものは、カステラに水ようかんに似た味(薄味のような感じ)の羊羹がはさんであるものでした。冷やした方が美味しいかも。甘さは控えめでした。
ネットでも食べたことがある人の感想がいろいろとあって、お店によってかなり味は違うようです。甘すぎる・・というものもあれば、すごく美味しいというものもあっていろいろ。味覚は人それぞれだからということもあるでしょうけど、店によってかなり違うことがうかがわれます。
形も三角、四角・・といろいろあるようです。
近年は、ほかにも美味しいお菓子がたくさんできて、作るのに手間のかかるシベリアは次第に姿を消していったようです。
昨年、宮崎駿監督の映画「風立ぬ」で主人公の堀越二郎が「シベリア二つおくれ」といって買い求めるシーンがあったそうで、それで、あれは何?と注目されて復活しているようです。九州ではなじみのないお菓子だったので、見過ごされた方も多かったでしょう。私は映画を見ていないので、本屋で映画の本を探し、そのシーンを確認いたしました。なるほど、三角形のシベリアを買い求めています。友人から「変なものを食うな」みたいなことを言われているので、大人の男が食べるものではなかったのかな・・という印象。女・子供のおやつだったのかしらね。
あんこ(羊羹)とカステラ・・・シベリアを眺めていて、思い出したお菓子があります。
四国の松山の銘菓、タルトです。
これもカステラとあんこの組み合わせ。
ただ、ロールケーキ状。
このお菓子のことは、また改めて書くことにいたしましょう。
シベリア・・が気になった方は、首都圏にはまだ作っているパン屋さんがあるようですよ。
検索してみてはいかがでしょう。
それから、関西ではロシア・という名前であったらしい・・という情報もいただきました。
これは未確認情報ですが、もし見かけたら教えてくださいね。
*****************************
~長崎街道(シュガーロード)について~
長崎街道(シュガーロード)は江戸時代に整備された脇街道の一つで、小倉の常盤橋を起点として長崎にいたるまでの路線です。長崎の出島に入った砂糖はこのルートを通って大阪や江戸に運ばれました。この砂糖が通った道沿いには、さまざまなお菓子が生まれることとなります。そして、時代が下って、炭鉱が華々しい頃にそのお菓子たちは筑豊で大きく花開く事になります。今では全国的に有名になっている【ひよこ】や【チロルチョコ】などは筑豊生まれのお菓子です。
私はこのシュガーロードを歩いて、お菓子が生まれた土壌、文化などを調べたいと常々思っていた・・というわけです。小倉~長崎までの宿場町に繁栄したお菓子、今でも残っている古いお菓子、新しい時代のお菓子、絶滅しかかっているお菓子など調べますよ。そして長崎まで調べたら、南蛮菓子の故郷、ポルトガルへ・・・と野望をいだいております。
******************************
このブログのサイドバーにあるテーマ 長崎街道(シュガーロード)で今まで書いたことを見ることができます.
当ブログ内の文章、写真、その他の無断転用、転載を固く禁じます
お菓子のことを検索していた時のこと。あるHPで、カステラとあんこの相性は思っているよりもよく、例えば、シベリアというお菓子が・・・・・云々。と書かれた文章を見つけました。
シベリア????
お菓子??
聞いたことがないぞ?
お菓子なら調べなくては・・
というわけで、今回のテーマは【シベリア】です。
写真は、横浜のコティーベーカリーから取り寄せたものです。

見ての通りの姿。
カステラとカステラの間に羊羹状のあんこ。
羊羹だからちゃんと固まっている。
あんこをはさんでいるのではなくて、トレーにカステラを敷いてそのうえに羊羹を流し込んで作るらしい。側面に漏れているところがあって、その製法を伺わせます。手間がかかっているお菓子です。
(お菓子・・といっていいかなあ。菓子パンの仲間になるのかも。明治から大正にかけて作っていたのはパン屋さんらしい。)
調べていると、
どうも明治時代の後半から大正時代にかけて生まれたお菓子で、ミルクホール(今でいう喫茶店のこと)での定番お菓子だったらしい。
いつ、どこで、だれが作り始めたのかは不明。
なぜこのお菓子の名前が【シベリア】なのか?
羊羹の部分がをツンドラを走るシベリア鉄道にみたてた・・・とか、シベリアの凍土をあらわしたとか・・・いろいろな説があるようです。コティーベーカリーのHPにいろんな説が紹介されてますので興味のある方は読んでみてください。
販売エリアは、首都圏を中心にした東日本と中部地方。近畿地方を中心とした西日本や九州ではなじみがないお菓子らしい。確かに、見たことはないが、Facebookでコメントをいただいた中に、九州で買ったというものがあって、全くないわけではないようです。
首都圏・・というと、これは東京出身の友人に聞いてみるのが早い・・・で、聞いてみましたところ、羊羹カステラといっていたということ。牛乳と一緒に食べるとおいしかったとのこと。私より若い友人が知っているということは、ごく最近まであちこちで販売されていたということでしょう。
味は、私が食べたコティーベーカリーのものは、カステラに水ようかんに似た味(薄味のような感じ)の羊羹がはさんであるものでした。冷やした方が美味しいかも。甘さは控えめでした。
ネットでも食べたことがある人の感想がいろいろとあって、お店によってかなり味は違うようです。甘すぎる・・というものもあれば、すごく美味しいというものもあっていろいろ。味覚は人それぞれだからということもあるでしょうけど、店によってかなり違うことがうかがわれます。
形も三角、四角・・といろいろあるようです。
近年は、ほかにも美味しいお菓子がたくさんできて、作るのに手間のかかるシベリアは次第に姿を消していったようです。
昨年、宮崎駿監督の映画「風立ぬ」で主人公の堀越二郎が「シベリア二つおくれ」といって買い求めるシーンがあったそうで、それで、あれは何?と注目されて復活しているようです。九州ではなじみのないお菓子だったので、見過ごされた方も多かったでしょう。私は映画を見ていないので、本屋で映画の本を探し、そのシーンを確認いたしました。なるほど、三角形のシベリアを買い求めています。友人から「変なものを食うな」みたいなことを言われているので、大人の男が食べるものではなかったのかな・・という印象。女・子供のおやつだったのかしらね。
あんこ(羊羹)とカステラ・・・シベリアを眺めていて、思い出したお菓子があります。
四国の松山の銘菓、タルトです。
これもカステラとあんこの組み合わせ。
ただ、ロールケーキ状。
このお菓子のことは、また改めて書くことにいたしましょう。
シベリア・・が気になった方は、首都圏にはまだ作っているパン屋さんがあるようですよ。
検索してみてはいかがでしょう。
それから、関西ではロシア・という名前であったらしい・・という情報もいただきました。
これは未確認情報ですが、もし見かけたら教えてくださいね。
*****************************
~長崎街道(シュガーロード)について~
長崎街道(シュガーロード)は江戸時代に整備された脇街道の一つで、小倉の常盤橋を起点として長崎にいたるまでの路線です。長崎の出島に入った砂糖はこのルートを通って大阪や江戸に運ばれました。この砂糖が通った道沿いには、さまざまなお菓子が生まれることとなります。そして、時代が下って、炭鉱が華々しい頃にそのお菓子たちは筑豊で大きく花開く事になります。今では全国的に有名になっている【ひよこ】や【チロルチョコ】などは筑豊生まれのお菓子です。
私はこのシュガーロードを歩いて、お菓子が生まれた土壌、文化などを調べたいと常々思っていた・・というわけです。小倉~長崎までの宿場町に繁栄したお菓子、今でも残っている古いお菓子、新しい時代のお菓子、絶滅しかかっているお菓子など調べますよ。そして長崎まで調べたら、南蛮菓子の故郷、ポルトガルへ・・・と野望をいだいております。
******************************
このブログのサイドバーにあるテーマ 長崎街道(シュガーロード)で今まで書いたことを見ることができます.
当ブログ内の文章、写真、その他の無断転用、転載を固く禁じます
タグ :シベリア 風立ぬ
水無月を買いに花月堂寿永へ・・・
2014年06月13日
今年も、博多水無月が販売される季節になりました。
博多水無月のことは昨年もこのブログにUPしています。
水無月のいわれとか、博多でどうして作られるようになったのか・・などを書いてますので、読んでくださいね。
水無月、買っておうちへ帰ろう♪→☆☆☆
水無月、買っておうちへ帰ろう♪その2→☆☆☆
昨年は、デパートでいくつかと、二日市の梅屋の水無月を買いました。
気になっていながら、行けなかった、春吉の花月堂寿永の水無月を食べれなかったのが心残りでした。
今日は、ふとその事を思い出したので、用事のついでに春吉まで行ってきました。
このお店の事も以前ブログで紹介していますので、読んでください。
唐津街道~福岡・博多 その3 花月堂寿永→☆☆☆
花月堂寿永の水無月は、とても品がよく、形もすっきりとしたものでした。
水無月の形は三角形。(これは氷の形を表す・・ともいわれています。)
食べるとちょっと固めの、弾力のあるわらび餅。小豆の粒がはいっていて、上品な甘さが口に残ります。私好みの甘さ。

ステキだなあ・・と思ったのは、笹の葉の巻き方。
切れ込みに葉の先を差しこんだだけですが、粋でしょ。

水無月は今年も7月まで販売されるようですよ。
気になった方は是非ご賞味ください。
博多水無月は、福岡市和菓子組合の和菓子屋さんが作ってます。
お店ごとに形なども違います。
決まり事は笹の葉、わらび粉と小豆を主原料にする・・ということ。
なので、お店の個性がでています。今年の新作・・もあるようですよ。
この機会に、福岡・博多の和菓子屋さんめぐりをするのも楽しいですね。
私が本日行ったお店のご紹介(参考までに)
花月堂寿永
福岡市博多区春吉2丁目7-20
℡092-761-0278

このお店は100年以上の歴史があるんですよ~。
京都のお店みたいでしょう。
のれんが季節によって色がかわるそうです。
夏は白。
お茶席のお菓子を中心につくっています。
*****************************
~長崎街道(シュガーロード)について~
長崎街道(シュガーロード)は江戸時代に整備された脇街道の一つで、小倉の常盤橋を起点として長崎にいたるまでの路線です。長崎の出島に入った砂糖はこのルートを通って大阪や江戸に運ばれました。この砂糖が通った道沿いには、さまざまなお菓子が生まれることとなります。そして、時代が下って、炭鉱が華々しい頃にそのお菓子たちは筑豊で大きく花開く事になります。今では全国的に有名になっている【ひよこ】や【チロルチョコ】などは筑豊生まれのお菓子です。
私はこのシュガーロードを歩いて、お菓子が生まれた土壌、文化などを調べたいと常々思っていた・・というわけです。小倉~長崎までの宿場町に繁栄したお菓子、今でも残っている古いお菓子、新しい時代のお菓子、絶滅しかかっているお菓子など調べますよ。そして長崎まで調べたら、南蛮菓子の故郷、ポルトガルへ・・・と野望をいだいております。
******************************
このブログのサイドバーにあるテーマ 長崎街道(シュガーロード)で今まで書いたことを見ることができます.
当ブログ内の文章、写真、その他の無断転用、転載を固く禁じます
博多水無月のことは昨年もこのブログにUPしています。
水無月のいわれとか、博多でどうして作られるようになったのか・・などを書いてますので、読んでくださいね。
水無月、買っておうちへ帰ろう♪→☆☆☆
水無月、買っておうちへ帰ろう♪その2→☆☆☆
昨年は、デパートでいくつかと、二日市の梅屋の水無月を買いました。
気になっていながら、行けなかった、春吉の花月堂寿永の水無月を食べれなかったのが心残りでした。
今日は、ふとその事を思い出したので、用事のついでに春吉まで行ってきました。
このお店の事も以前ブログで紹介していますので、読んでください。
唐津街道~福岡・博多 その3 花月堂寿永→☆☆☆
花月堂寿永の水無月は、とても品がよく、形もすっきりとしたものでした。
水無月の形は三角形。(これは氷の形を表す・・ともいわれています。)
食べるとちょっと固めの、弾力のあるわらび餅。小豆の粒がはいっていて、上品な甘さが口に残ります。私好みの甘さ。

ステキだなあ・・と思ったのは、笹の葉の巻き方。
切れ込みに葉の先を差しこんだだけですが、粋でしょ。

水無月は今年も7月まで販売されるようですよ。
気になった方は是非ご賞味ください。
博多水無月は、福岡市和菓子組合の和菓子屋さんが作ってます。
お店ごとに形なども違います。
決まり事は笹の葉、わらび粉と小豆を主原料にする・・ということ。
なので、お店の個性がでています。今年の新作・・もあるようですよ。
この機会に、福岡・博多の和菓子屋さんめぐりをするのも楽しいですね。
私が本日行ったお店のご紹介(参考までに)
花月堂寿永
福岡市博多区春吉2丁目7-20
℡092-761-0278

このお店は100年以上の歴史があるんですよ~。
京都のお店みたいでしょう。
のれんが季節によって色がかわるそうです。
夏は白。
お茶席のお菓子を中心につくっています。
*****************************
~長崎街道(シュガーロード)について~
長崎街道(シュガーロード)は江戸時代に整備された脇街道の一つで、小倉の常盤橋を起点として長崎にいたるまでの路線です。長崎の出島に入った砂糖はこのルートを通って大阪や江戸に運ばれました。この砂糖が通った道沿いには、さまざまなお菓子が生まれることとなります。そして、時代が下って、炭鉱が華々しい頃にそのお菓子たちは筑豊で大きく花開く事になります。今では全国的に有名になっている【ひよこ】や【チロルチョコ】などは筑豊生まれのお菓子です。
私はこのシュガーロードを歩いて、お菓子が生まれた土壌、文化などを調べたいと常々思っていた・・というわけです。小倉~長崎までの宿場町に繁栄したお菓子、今でも残っている古いお菓子、新しい時代のお菓子、絶滅しかかっているお菓子など調べますよ。そして長崎まで調べたら、南蛮菓子の故郷、ポルトガルへ・・・と野望をいだいております。
******************************
このブログのサイドバーにあるテーマ 長崎街道(シュガーロード)で今まで書いたことを見ることができます.
当ブログ内の文章、写真、その他の無断転用、転載を固く禁じます
KBCアサデス 九州山口にでました
2014年03月26日
ブログにお菓子のことを書きつづけて1年半くらいになります。
長崎は江戸時代、鎖国をしていた我が国で唯一の外の世界に開かれた町でした。
出島には、いろいろなものが入ってきました。その中に、砂糖がありました。
江戸や大坂にむけて運ばれていった砂糖。海路、陸路を使って運ばれていきました。
長崎街道は、そんな歴史から、別名シュガーロードと呼ばれています。
砂糖が通った道沿いには、甘いお菓子の文化も広がっていきました。
時代が変わって近代産業が盛んになりしころ、その沿線に、一大消費地が出現し、それによってますますお菓子は発展していきます。
長崎のカステラ、佐賀のまるぼうろ、筑豊のひよ子や千鳥饅頭などなど。
そんなお菓子を取り巻く歴史や、生まれた町の背景、誕生のお話・・・などに、魅力を感じてはまり込んだ郷土菓子の世界。まるで仕事のように、頼まれもしないのに、ブログに書きつづけています。
そんなブログを、たまたま、お菓子のことを検索していた、KBCアサデスの製作スタッフさんが見つけてくださいました。
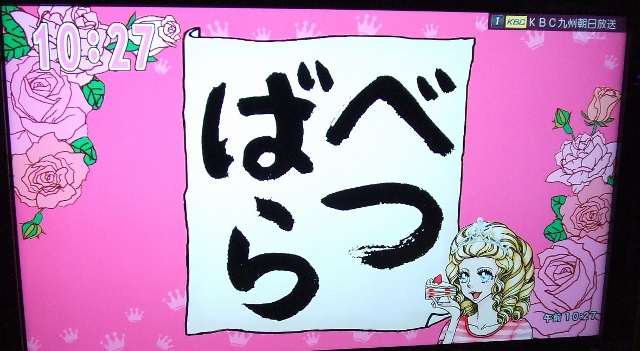
ちょうど、「べつばら」という企画で、お菓子とそのお菓子を紹介してくれる人を探していたそうです。「べつばら」というのは、ランチなどを食べた後にでも、ペロリと食べれるお菓子・・。ほらよく、言うじゃない。ケーキはべつばら・・って。それ・・です。私はべつばらを紹介する、ベツバラジェンヌ・・ということになるらしいのです。
で、電話で急に何かありませんか?…・と尋ねられ(たくさん食べているのに、急に尋ねられると意外と思いつかないものですw)いくつか候補をあげて、その中から、長崎のホンダ洋菓子店の「スイスロール」を・・ということになりました。
一応、郷土菓子研究家としてのデビューです。
長崎・・というのもかなり感慨深い(私は長崎生まれです)
・・・というわけで、19日に長崎ロケ・・・に行ってきました。(その内容が本日、放映されました)

みよ♪ この晴れ姿(大笑)
場所は思案橋です。

レポーターの三好さんと、やり取りをしているところ。
郷土菓子研究をしているんだよ~~・という話。
べつばら・・・ということなので、その前に、ほんばら・・をということで、長崎名物、トルコライスを「つる茶ん」で食べました。このお店はトルコライス発祥のお店。創業大正14年の老舗です。

これを平らげた後に、いよいよ、べつばらのロケがスタート・・となりました。
今回、お邪魔した、ホンダ洋菓子店(http://swiss-roll.com/)は、長崎の公会堂前のあたりにある、創業90年くらいになるお店です。(創業大正14年)
今のオーナーは3代目。オーナーのお父様が初代、お兄さんが2代目だそうです。
初代は、梅月堂(シースクリームで有名なお店)で修業をなさったそうで、その後、洋菓子のお店を開かれたそうです。
長崎で初めての洋菓子店だったそうです。
「スイスロール」は、2代目のお兄さんが考案。
番組でも紹介されていましたが、こちらのスイスロールは、中にアップルパイが入っています。ロールケーキとアップルパイの二つの味が楽しめる優れもの。
なぜ、このようなお菓子を作るようになったかというと、作った当時(昭和33年)は、アップルパイがまだメジャーではなかったので、それを広めるためということと、当時のアップルパイのなかには、スポンジ生地をいれてつくっていたのだけど、これを逆にして、スポンジ生地で巻いてみたらどうだろうか・・と思ったからだそうです。

これが、スイスロールです。
スイス・・とつけたのは、バタークリームを使っているので、バター→酪農→スイス・・と連想して名づけたとのことでした。バタークリームというと、私と同じくらいの年齢の人にとっては懐かしいかもね。私が小さいときには、デコレーションケーキにはバタークリームでした。当時はまだ、生クリームがなかった(あったかもしれないけれど、メジャーではなかったのです)
バタークリームは、生クリームより日持ちがしますが、食べると重たい感じがします。(生クリームよりは)しかし、このスイスロールのバタークリームはとても上品で、甘い(といっても控えめ)中にほんのり塩味がしててとても美味。もたれないです。
写真のロールケーキの大きさは小。
他にも、 中ロールと大ロールがあります。
お取り寄せできますよ。
あと一切れサイズもあります。(これはお取り寄せは?ですが、長崎に行ったら試してみて)
テレビでも言いましたが、きめの細かいスポンジを食べていくと、ほんのりと上品なクリームにあたり、それで口の中が甘くなったら、リンゴがやってきて、その酸味でリフレッシュ。また食べる・・・となり、飽きない味なのです。
ロケの合間に、オーナーさんと奥様とお話がたくさんでき、長崎のおくんちのこととか、いろいろと聞きたかったことをお尋ねできて、私のお菓子の調査にとっても、とても有意義でした。ありがとうございました。長崎に行ったらまた、よらせていただきます。
それにしても、ブログから駒・・・・といった出来事に、狂喜乱舞(気持ちの上で・・・)の様相になった一週間。ずっと書きつづけたことに対しての、ご褒美やね・・。
今更ながら、継続は力・・・ということを、しみじみと感じた出来事でありました。
*****************************
~長崎街道(シュガーロード)について~
長崎街道(シュガーロード)は江戸時代に整備された脇街道の一つで、小倉の常盤橋を起点として長崎にいたるまでの路線です。長崎の出島に入った砂糖はこのルートを通って大阪や江戸に運ばれました。この砂糖が通った道沿いには、さまざまなお菓子が生まれることとなります。そして、時代が下って、炭鉱が華々しい頃にそのお菓子たちは筑豊で大きく花開く事になります。今では全国的に有名になっている【ひよこ】や【チロルチョコ】などは筑豊生まれのお菓子です。
私はこのシュガーロードを歩いて、お菓子が生まれた土壌、文化などを調べたいと常々思っていた・・というわけです。小倉~長崎までの宿場町に繁栄したお菓子、今でも残っている古いお菓子、新しい時代のお菓子、絶滅しかかっているお菓子など調べますよ。そして長崎まで調べたら、南蛮菓子の故郷、ポルトガルへ・・・と野望をいだいております。
******************************
このブログのサイドバーにあるテーマで今まで書いたことを見ることができます.
当ブログ内の文章、写真、その他の無断転用、転載を固く禁じます
長崎は江戸時代、鎖国をしていた我が国で唯一の外の世界に開かれた町でした。
出島には、いろいろなものが入ってきました。その中に、砂糖がありました。
江戸や大坂にむけて運ばれていった砂糖。海路、陸路を使って運ばれていきました。
長崎街道は、そんな歴史から、別名シュガーロードと呼ばれています。
砂糖が通った道沿いには、甘いお菓子の文化も広がっていきました。
時代が変わって近代産業が盛んになりしころ、その沿線に、一大消費地が出現し、それによってますますお菓子は発展していきます。
長崎のカステラ、佐賀のまるぼうろ、筑豊のひよ子や千鳥饅頭などなど。
そんなお菓子を取り巻く歴史や、生まれた町の背景、誕生のお話・・・などに、魅力を感じてはまり込んだ郷土菓子の世界。まるで仕事のように、頼まれもしないのに、ブログに書きつづけています。
そんなブログを、たまたま、お菓子のことを検索していた、KBCアサデスの製作スタッフさんが見つけてくださいました。
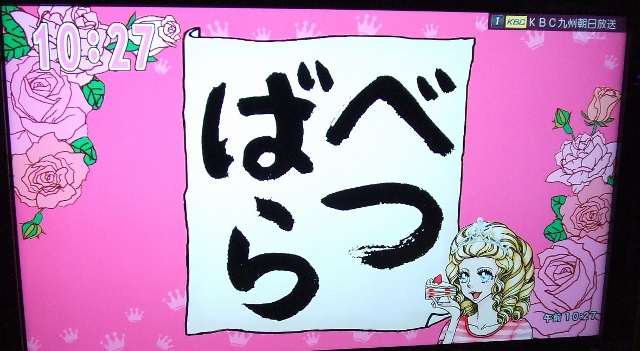
ちょうど、「べつばら」という企画で、お菓子とそのお菓子を紹介してくれる人を探していたそうです。「べつばら」というのは、ランチなどを食べた後にでも、ペロリと食べれるお菓子・・。ほらよく、言うじゃない。ケーキはべつばら・・って。それ・・です。私はべつばらを紹介する、ベツバラジェンヌ・・ということになるらしいのです。
で、電話で急に何かありませんか?…・と尋ねられ(たくさん食べているのに、急に尋ねられると意外と思いつかないものですw)いくつか候補をあげて、その中から、長崎のホンダ洋菓子店の「スイスロール」を・・ということになりました。
一応、郷土菓子研究家としてのデビューです。
長崎・・というのもかなり感慨深い(私は長崎生まれです)
・・・というわけで、19日に長崎ロケ・・・に行ってきました。(その内容が本日、放映されました)

みよ♪ この晴れ姿(大笑)
場所は思案橋です。

レポーターの三好さんと、やり取りをしているところ。
郷土菓子研究をしているんだよ~~・という話。
べつばら・・・ということなので、その前に、ほんばら・・をということで、長崎名物、トルコライスを「つる茶ん」で食べました。このお店はトルコライス発祥のお店。創業大正14年の老舗です。

これを平らげた後に、いよいよ、べつばらのロケがスタート・・となりました。
今回、お邪魔した、ホンダ洋菓子店(http://swiss-roll.com/)は、長崎の公会堂前のあたりにある、創業90年くらいになるお店です。(創業大正14年)
今のオーナーは3代目。オーナーのお父様が初代、お兄さんが2代目だそうです。
初代は、梅月堂(シースクリームで有名なお店)で修業をなさったそうで、その後、洋菓子のお店を開かれたそうです。
長崎で初めての洋菓子店だったそうです。
「スイスロール」は、2代目のお兄さんが考案。
番組でも紹介されていましたが、こちらのスイスロールは、中にアップルパイが入っています。ロールケーキとアップルパイの二つの味が楽しめる優れもの。
なぜ、このようなお菓子を作るようになったかというと、作った当時(昭和33年)は、アップルパイがまだメジャーではなかったので、それを広めるためということと、当時のアップルパイのなかには、スポンジ生地をいれてつくっていたのだけど、これを逆にして、スポンジ生地で巻いてみたらどうだろうか・・と思ったからだそうです。

これが、スイスロールです。
スイス・・とつけたのは、バタークリームを使っているので、バター→酪農→スイス・・と連想して名づけたとのことでした。バタークリームというと、私と同じくらいの年齢の人にとっては懐かしいかもね。私が小さいときには、デコレーションケーキにはバタークリームでした。当時はまだ、生クリームがなかった(あったかもしれないけれど、メジャーではなかったのです)
バタークリームは、生クリームより日持ちがしますが、食べると重たい感じがします。(生クリームよりは)しかし、このスイスロールのバタークリームはとても上品で、甘い(といっても控えめ)中にほんのり塩味がしててとても美味。もたれないです。
写真のロールケーキの大きさは小。
他にも、 中ロールと大ロールがあります。
お取り寄せできますよ。
あと一切れサイズもあります。(これはお取り寄せは?ですが、長崎に行ったら試してみて)
テレビでも言いましたが、きめの細かいスポンジを食べていくと、ほんのりと上品なクリームにあたり、それで口の中が甘くなったら、リンゴがやってきて、その酸味でリフレッシュ。また食べる・・・となり、飽きない味なのです。
ロケの合間に、オーナーさんと奥様とお話がたくさんでき、長崎のおくんちのこととか、いろいろと聞きたかったことをお尋ねできて、私のお菓子の調査にとっても、とても有意義でした。ありがとうございました。長崎に行ったらまた、よらせていただきます。
それにしても、ブログから駒・・・・といった出来事に、狂喜乱舞(気持ちの上で・・・)の様相になった一週間。ずっと書きつづけたことに対しての、ご褒美やね・・。
今更ながら、継続は力・・・ということを、しみじみと感じた出来事でありました。
*****************************
~長崎街道(シュガーロード)について~
長崎街道(シュガーロード)は江戸時代に整備された脇街道の一つで、小倉の常盤橋を起点として長崎にいたるまでの路線です。長崎の出島に入った砂糖はこのルートを通って大阪や江戸に運ばれました。この砂糖が通った道沿いには、さまざまなお菓子が生まれることとなります。そして、時代が下って、炭鉱が華々しい頃にそのお菓子たちは筑豊で大きく花開く事になります。今では全国的に有名になっている【ひよこ】や【チロルチョコ】などは筑豊生まれのお菓子です。
私はこのシュガーロードを歩いて、お菓子が生まれた土壌、文化などを調べたいと常々思っていた・・というわけです。小倉~長崎までの宿場町に繁栄したお菓子、今でも残っている古いお菓子、新しい時代のお菓子、絶滅しかかっているお菓子など調べますよ。そして長崎まで調べたら、南蛮菓子の故郷、ポルトガルへ・・・と野望をいだいております。
******************************
このブログのサイドバーにあるテーマで今まで書いたことを見ることができます.
当ブログ内の文章、写真、その他の無断転用、転載を固く禁じます
ショック!二日市温泉 中村屋の火事
2014年01月24日
今日、たまたま通りかかった二日市温泉。
気がつけば、中村屋が真っ黒に焼けてる。
知らなかったのだけど、22日の午後、火事で焼けたらしい。
22日といえば、雪の日で、私はシュガーロードのモニターツアーに参加していた日。
復活は難しいだろう・・というのが大方の見方のよう。
あの、天拝饅頭はもう食べれない。とてもショック。
とても悲しい気持ちでいっぱいです(TT)
昨年、天拝饅頭の話などお聞きしてこのブログにもUPしてます。
こちらをご覧下さい→☆☆☆

気がつけば、中村屋が真っ黒に焼けてる。
知らなかったのだけど、22日の午後、火事で焼けたらしい。
22日といえば、雪の日で、私はシュガーロードのモニターツアーに参加していた日。
復活は難しいだろう・・というのが大方の見方のよう。
あの、天拝饅頭はもう食べれない。とてもショック。
とても悲しい気持ちでいっぱいです(TT)
昨年、天拝饅頭の話などお聞きしてこのブログにもUPしてます。
こちらをご覧下さい→☆☆☆

タグ :二日市温泉 天拝饅頭 中村屋
薩摩の郷土菓子 けせん団子
2013年10月26日

お向かいさんからお団子をいただきました。
見ると「けせん団子」と書いてある・・・?けせん??ってな~に?
郷土菓子研究家・・としては、これは捨て置けぬ(笑)
というわけで、ちょいと調べてみました。
けせん団子は、薩摩地方の郷土菓子です。
けせん・・というのは肉桂(ニッキ)のことです。
小豆と砂糖と米粉で作ったお団子をけせんの葉ではさんで、蒸したお菓子のようです。
袋をあけると、ほのかにシナモンの香がします。(肉桂はシナモンの仲間です)この香が南の地方のお菓子の雰囲気を醸し出しています。

こんな感じのお団子です。
細長く、中は黒いお団子。
柏餅の色を黒くして細長くして・・みたいなお団子です。
きっと肉桂の葉には殺菌作用なんかもあるんでしょうね。
日持ちがしそうな気がします。(あくまでも私がそう思っているだけでまだ調べてません)
薩摩菓子は、北部九州ではみかけない南九州特有のお菓子がたくさんあります。
なんといっても、黒砂糖の産地をもってますからね。色の黒いお菓子が多いようなイメージです。それから、かるかんのようなお菓子のイメージ。素朴で飾らないお菓子が魅力的なんです。そのうち調べてみたいと思っています。
*****************************
~長崎街道(シュガーロード)について~
長崎街道(シュガーロード)は江戸時代に整備された脇街道の一つで、小倉の常盤橋を起点として長崎にいたるまでの路線です。長崎の出島に入った砂糖はこのルートを通って大阪や江戸に運ばれました。この砂糖が通った道沿いには、さまざまなお菓子が生まれることとなります。そして、時代が下って、炭鉱が華々しい頃にそのお菓子たちは筑豊で大きく花開く事になります。今では全国的に有名になっている【ひよこ】や【チロルチョコ】などは筑豊生まれのお菓子です。
私はこのシュガーロードを歩いて、お菓子が生まれた土壌、文化などを調べたいと常々思っていた・・というわけです。小倉~長崎までの宿場町に繁栄したお菓子、今でも残っている古いお菓子、新しい時代のお菓子、絶滅しかかっているお菓子など調べますよ。そして長崎まで調べたら、南蛮菓子の故郷、ポルトガルへ・・・と野望をいだいております。
******************************
このブログのサイドバーにあるテーマ 長崎街道(シュガーロード)・唐津街道で今まで書いたことを見ることができます。
長崎街道に当てはまらないお菓子などのことは、テーマ、お菓子ストーリー・スイーツ女子の日々に書いています。
当ブログ内の文章、写真、その他の無断転用、転載を固く禁じます
如水庵 黒田藩太鼓焼
2013年09月03日
長崎街道(シュガーロード)のお菓子を調べているうちに、地元の福岡(博多)に残るお菓子や和菓子屋も気になってきました。
一番古いといわれていた松屋は昨年秋に閉店してしまったしね~~・・・。
今残っているお菓子屋で一番古いところはどこだろう??
そう思っていたところに、五十二萬石本舗 如水庵がどうも古いらしい・・。創業四二〇年の軌跡をまとめた本が有るらしい・・・ということをしりました。今ではもう販売されていないようなので、古書で探していたところ、見つけることができ、この夏の読書の楽しみの一つになったのでした。
本によると、かなり古いようで、博多の歴史とも重なるとても興味深いものでした。ただ、はっきりとした裏づけが取れない部分があるようなのです。今後の研究を待ちたいところです。
そんな本を読んだりしているので、このお店のオープンにはもちろん反応いたします(笑)
如水庵 黒田藩太鼓焼 のお店です。
太鼓焼は、回転焼のことです。
このお饅頭は地方によっていろいろと呼び名がありますね。
今川焼きとか御座候とか・・・。福岡では蜂楽饅頭というのもあります。
みんな同じお饅頭。

黒田家の家紋の使用を許されている如水庵らしい焼印
このしるしが入っているのが黒餡でした。

厚みは3cm強くらい。アンコもしっかりはいってます。
普通の回転焼きより厚みがしっかりありますね。白餡は甘味もあり、華やかな感じ。黒餡は白餡より甘さ控えめ。
来年の大河ドラマを見据えての出店でしょうか?
場所は、西鉄福岡駅の北口改札の傍ですから、ちょっと甘い物が欲しいときにいいかもです。
お値段は1個105円でした。お店はAM10時からPM10時まで。
*****************************
~長崎街道(シュガーロード)に魅せられて~
長崎街道(シュガーロード)は江戸時代に整備された脇街道の一つで、小倉の常盤橋を起点として長崎にいたるまでの路線です。長崎の出島に入った砂糖はこのルートを通って大阪や江戸に運ばれました。この砂糖が通った道沿いには、さまざまなお菓子が生まれることとなります。そして、時代が下って、炭鉱が華々しい頃にそのお菓子たちは筑豊で大きく花開く事になります。今では全国的に有名になっている【ひよこ】や【チロルチョコ】などは筑豊生まれのお菓子です。
私はこのシュガーロードを歩いて、お菓子が生まれた土壌、文化などを調べたいと常々思っていた・・というわけです。小倉~長崎までの宿場町に繁栄したお菓子、今でも残っている古いお菓子、新しい時代のお菓子、絶滅しかかっているお菓子など調べますよ。そして長崎まで調べたら、南蛮菓子の故郷、ポルトガルへ・・・と野望をいだいております。
******************************
このブログのサイドバーにあるテーマ 長崎街道(シュガーロード)・唐津街道・薩摩街道で今まで書いたことを見ることができます。
街道に当てはまらないお菓子などのことは、テーマ、お菓子ストーリー・スイーツ女子の日々に書いています。
当ブログ内の文章、写真、その他の無断転用、転載を固く禁じます
熊久で牛蒡餅を買う♪
2013年08月20日
なんとなく、甘いお菓子が食べたくなった。
それも上品でしつこくない甘さのものが・・。
で、思い出したのが、平戸の牛蒡餅。
あの、砂糖甘い、優しい味が恋しくなった。
だが、平戸は遠く・・・・と思っていて思い出したのが、
平戸の熊屋さんが言っていたこと。
「福岡に支店があります。赤坂というところです。メインの通りからはずれたところにあります。でも大通りに面してますよ。わかりますか?」
これを聞いた私は、「あ~メインの通りは明治通だから、きっと昭和通沿いなんだな・・」と思ったことと、メインの通りからはずれてます・・なんて、ちょっと笑ったことも思いだした。
で検索。やっぱり昭和通沿い。平和台通りの交差点の角でわかりやすい。
というわけで、牛蒡餅ふたたびとなったわけ。
暑いのにね。食い気は、暑さにも勝つ!!てか。(大笑)
【熊久】は平戸の熊屋の支店。熊屋はいろいろとお菓子をつくっているが、中でも牛蒡餅が有名。平戸では、話好きなお店の方に楽しい時間をいただいた。ちなみに、熊屋は平戸で250年続く老舗。平戸はこんな感じであちこちに100年以上のお店が残っていて、ちょっとヨーロッパを思わせるのは、そんなところからもきているのかもしれない(個人的な感想だけど)
(平戸でのことは、テーマ 長崎街道(シュガーロード)の中に書いてますのでご覧下さい)
その時に出た話が先に書いたこととなる。よかった。教えて頂いてて。

お店の入り口。
ちょっとモダンな感じ。
中はお菓子の販売と喫茶もできるようになっている。
(平戸の熊屋もお店で買ったものを食べることが出来るようになっているので同じ感じかな)
お店では若い女性のスタッフが応対してくれた。

牛蒡餅は5種類 1個105円也
上の段 黒糖味 白糖味
下の段 桜味 浜塩味 抹茶味

5本入り 5種類入っているから全部味見したい方におすすめ
お値段も420円で一本分お得になっている。

これが中身
賞味期限は3日間。生菓子だから日にちがたつと固くなる。
そのまま食べてもおいしいけれど、この時期はちょっとだけ冷やすと美味
ただ、あまり冷蔵庫に入れていると固くなるかも・・(要注意)
以前も書いたのだけれど、牛蒡餅は、形が牛蒡に似ているから名づけられたお菓子。牛蒡ははいってませんので。私は名前を聞いただけでちょっと敬遠してた。牛蒡の味がするのか・・と思って。大丈夫。牛蒡の味はしません(笑)
牛蒡餅を食べたら季節がよくなったら、また平戸に行こうか・・と、ふと思ってしまった。
あの、ポルトガルを思わせる西の海がちょいと恋しくなってしまった。
私的にはポルトガルだけど、今年の平戸はユニオンジャックだらけ。
平戸英国商館設置400年の記念の年なのだ。
まあ、それはそれでよしとする。
*****************************
~長崎街道(シュガーロード)に魅せられて~
長崎街道(シュガーロード)は江戸時代に整備された脇街道の一つで、小倉の常盤橋を起点として長崎にいたるまでの路線です。長崎の出島に入った砂糖はこのルートを通って大阪や江戸に運ばれました。この砂糖が通った道沿いには、さまざまなお菓子が生まれることとなります。そして、時代が下って、炭鉱が華々しい頃にそのお菓子たちは筑豊で大きく花開く事になります。今では全国的に有名になっている【ひよこ】や【チロルチョコ】などは筑豊生まれのお菓子です。
私はこのシュガーロードを歩いて、お菓子が生まれた土壌、文化などを調べたいと常々思っていた・・というわけです。小倉~長崎までの宿場町に繁栄したお菓子、今でも残っている古いお菓子、新しい時代のお菓子、絶滅しかかっているお菓子など調べますよ。そして長崎まで調べたら、南蛮菓子の故郷、ポルトガルへ・・・と野望をいだいております。
******************************
このブログのサイドバーにあるテーマ 長崎街道(シュガーロード)・唐津街道・薩摩街道で今まで書いたことを見ることができます。
街道に当てはまらないお菓子などのことは、テーマ、お菓子ストーリーに書いています。
当ブログ内の文章、写真、その他の無断転用、転載を固く禁じます
それも上品でしつこくない甘さのものが・・。
で、思い出したのが、平戸の牛蒡餅。
あの、砂糖甘い、優しい味が恋しくなった。
だが、平戸は遠く・・・・と思っていて思い出したのが、
平戸の熊屋さんが言っていたこと。
「福岡に支店があります。赤坂というところです。メインの通りからはずれたところにあります。でも大通りに面してますよ。わかりますか?」
これを聞いた私は、「あ~メインの通りは明治通だから、きっと昭和通沿いなんだな・・」と思ったことと、メインの通りからはずれてます・・なんて、ちょっと笑ったことも思いだした。
で検索。やっぱり昭和通沿い。平和台通りの交差点の角でわかりやすい。
というわけで、牛蒡餅ふたたびとなったわけ。
暑いのにね。食い気は、暑さにも勝つ!!てか。(大笑)
【熊久】は平戸の熊屋の支店。熊屋はいろいろとお菓子をつくっているが、中でも牛蒡餅が有名。平戸では、話好きなお店の方に楽しい時間をいただいた。ちなみに、熊屋は平戸で250年続く老舗。平戸はこんな感じであちこちに100年以上のお店が残っていて、ちょっとヨーロッパを思わせるのは、そんなところからもきているのかもしれない(個人的な感想だけど)
(平戸でのことは、テーマ 長崎街道(シュガーロード)の中に書いてますのでご覧下さい)
その時に出た話が先に書いたこととなる。よかった。教えて頂いてて。

お店の入り口。
ちょっとモダンな感じ。
中はお菓子の販売と喫茶もできるようになっている。
(平戸の熊屋もお店で買ったものを食べることが出来るようになっているので同じ感じかな)
お店では若い女性のスタッフが応対してくれた。

牛蒡餅は5種類 1個105円也
上の段 黒糖味 白糖味
下の段 桜味 浜塩味 抹茶味

5本入り 5種類入っているから全部味見したい方におすすめ
お値段も420円で一本分お得になっている。

これが中身
賞味期限は3日間。生菓子だから日にちがたつと固くなる。
そのまま食べてもおいしいけれど、この時期はちょっとだけ冷やすと美味
ただ、あまり冷蔵庫に入れていると固くなるかも・・(要注意)
以前も書いたのだけれど、牛蒡餅は、形が牛蒡に似ているから名づけられたお菓子。牛蒡ははいってませんので。私は名前を聞いただけでちょっと敬遠してた。牛蒡の味がするのか・・と思って。大丈夫。牛蒡の味はしません(笑)
牛蒡餅を食べたら季節がよくなったら、また平戸に行こうか・・と、ふと思ってしまった。
あの、ポルトガルを思わせる西の海がちょいと恋しくなってしまった。
私的にはポルトガルだけど、今年の平戸はユニオンジャックだらけ。
平戸英国商館設置400年の記念の年なのだ。
まあ、それはそれでよしとする。
*****************************
~長崎街道(シュガーロード)に魅せられて~
長崎街道(シュガーロード)は江戸時代に整備された脇街道の一つで、小倉の常盤橋を起点として長崎にいたるまでの路線です。長崎の出島に入った砂糖はこのルートを通って大阪や江戸に運ばれました。この砂糖が通った道沿いには、さまざまなお菓子が生まれることとなります。そして、時代が下って、炭鉱が華々しい頃にそのお菓子たちは筑豊で大きく花開く事になります。今では全国的に有名になっている【ひよこ】や【チロルチョコ】などは筑豊生まれのお菓子です。
私はこのシュガーロードを歩いて、お菓子が生まれた土壌、文化などを調べたいと常々思っていた・・というわけです。小倉~長崎までの宿場町に繁栄したお菓子、今でも残っている古いお菓子、新しい時代のお菓子、絶滅しかかっているお菓子など調べますよ。そして長崎まで調べたら、南蛮菓子の故郷、ポルトガルへ・・・と野望をいだいております。
******************************
このブログのサイドバーにあるテーマ 長崎街道(シュガーロード)・唐津街道・薩摩街道で今まで書いたことを見ることができます。
街道に当てはまらないお菓子などのことは、テーマ、お菓子ストーリーに書いています。
当ブログ内の文章、写真、その他の無断転用、転載を固く禁じます



